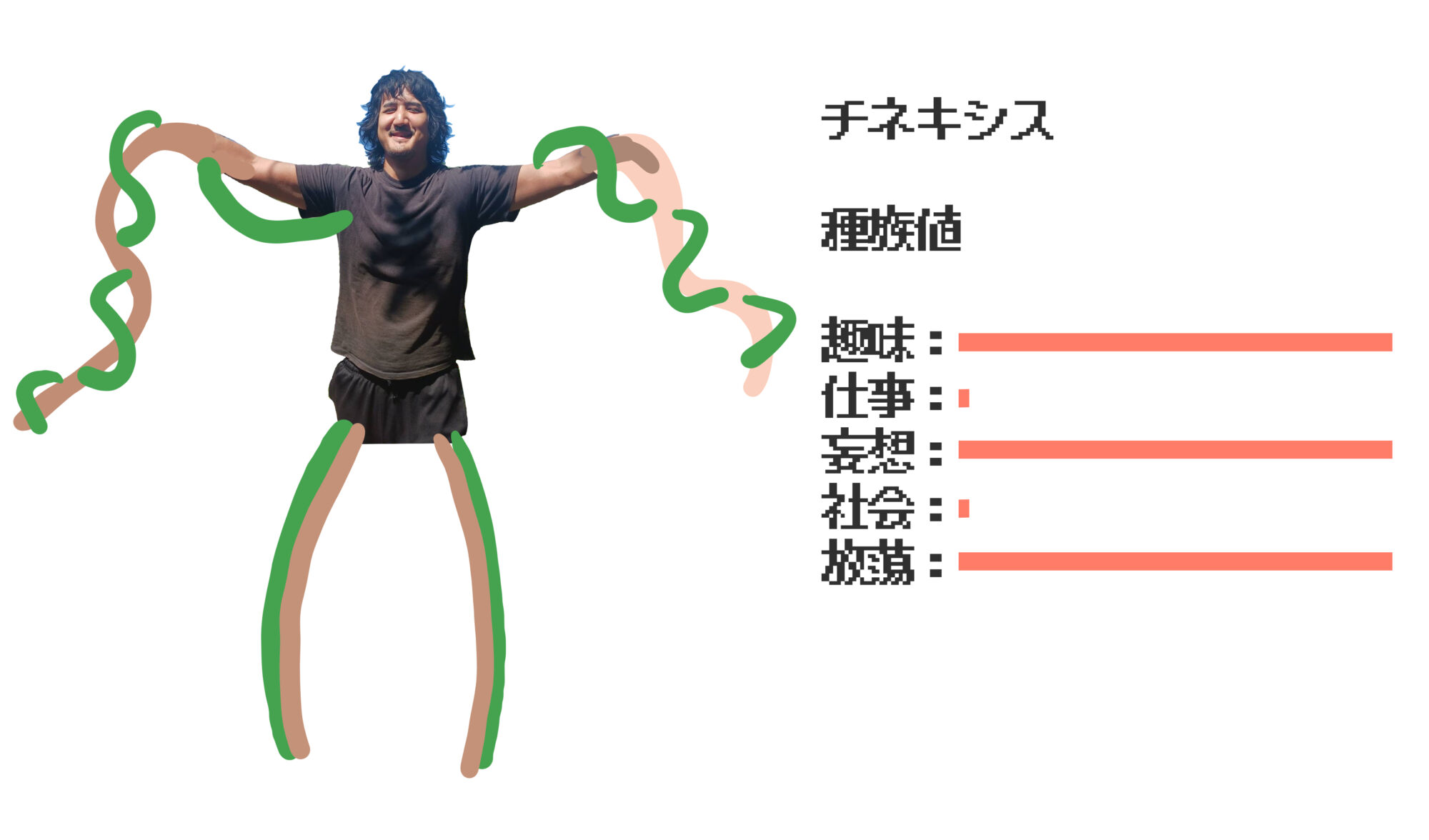こんにちは チネヌンコです。
最近読んでる本で、特に感動 というか有益な知恵になった書物だったので、紹介しようと思います。
貧困と脳 「働かない」のではなく「働けない」
著者 鈴木大介
https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344987531/
一言で説明すると、この本は 「精神障害(発達障害)の解像度を非常に高める」一冊です。
かなりのボリュームで当事者の脳内で何が起こっているのか、なぜ異常な行動をとるのかが説明されています。
私も、読んでいて身に覚えがあることばかりで、共感した部分もあります。
ただ 本書にある わかりやすい欠点が、「まず健常者は一切そういう分野に興味関心がなく、肝心の当事者(少なくとも筆者が想定する読者?)にとっては 共感する部分も多いが読破は難しいだろう」というものですw
とにかくページが多いw確かに、障害当事者にとって、社会に物申したいことは本一冊じゃすまないのはわかるけども
①中途障碍者(脳梗塞)の知識人による、非常に洗練された言語化
脳の障害当事者にとっては、うすうす感じていたことでも、周囲にわかってもらうための説明ができないようなことが、この本には非常に丁寧に、「元 健常者目線」と「障碍者目線」で書かれています。
鈴木大介さん(著者)のことは、今回初めて知ったんですが、以前にベストセラーの「最貧困女子」という本を記されていた方ということで、貧困層に陥るような、ヤバい人間の解像度が高いです。
そのヤバい人間の共通点に、精神障害、発達障害が多くみられるというので、貧困とはまさに 病魔そのものである。と感じました。
感想文書いてるチネヌンコも当事者かつ貧困者なので、ぶっちゃけこの本を買った理由も、貧困と脳の相関は必ずあるという確信を頑なにしたいという「バイアス強化」が元にありました。それがこの本を読んだことで、障碍者(一部特例を除く)が、
・なぜ あんなにも仕事ができない…遅い、サボりガチなのか
・なぜ 遊ぶことはできても働けないのか
・なぜ 時間も約束も碌に守らず、不真面目なのか
以上の 健常者目線でいう所謂「社会不適合者」「怠け者」「ろくでなし」の人間。
実際、障碍者が裏で どれだけ血のにじむ努力をしても それらが全くできないことの 圧倒的不可能感の説明。
・仕事ができない…遅い、サボりガチ
・遊ぶことはできても働けない
・時間も約束も碌に守れず、真面目?
少なくとも私には、それらの答え合わせを この本がしてくれたような気がしました。
②脳欠陥あるある
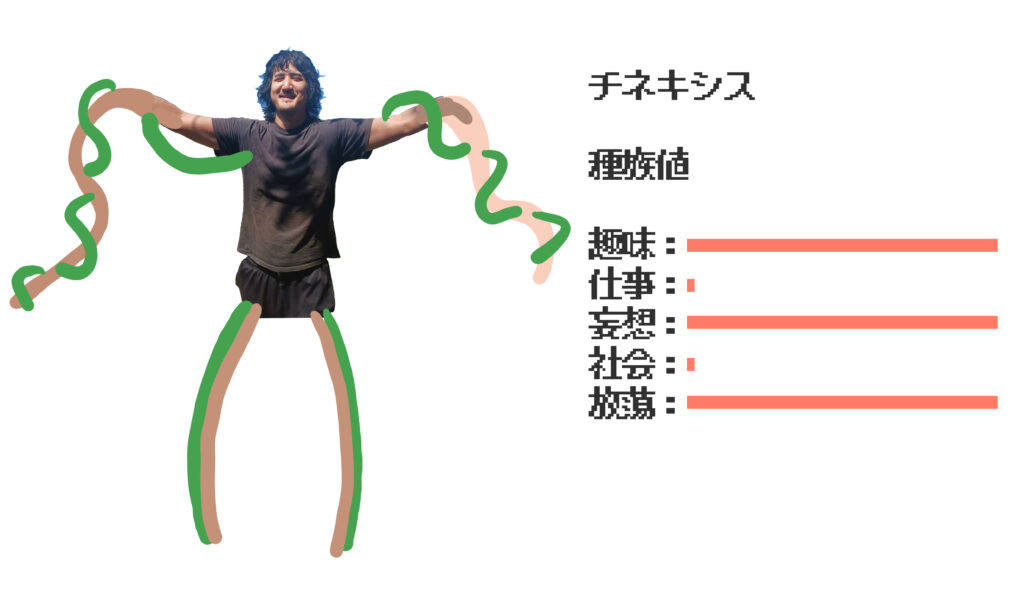
健常者の脳が完璧な状態だとして、障碍者の脳は一律で能力が下がっているわけではなく、「一部」低下または不能な状態です。
例えば私の場合、会社等の組織での「義務、雑務、時間拘束」が非常に苦痛になります。それらの環境に長時間晒されると〇にます。
筆者の鈴木さんも、もともとライターとして非常に能力の高い人間だったのが、脳梗塞の後遺症をきっかけに能力があべこべになってしまった。この本では、それまで取材してきた貧困な人たちや自身の体験から、「障碍者の脳内で何が起こっているのか」を多角的に精度高めの描写できている気がします。
圧倒的に雑務が苦手、会話が苦手、情報の多い場所が苦手…わっかる~てなりました。仕事で健常者が普通にこなしていることは 私には無理です。
なのに、できる業務もある…私の場合「絵 文章 運動」は 多分健常者と同等にこなせます。
命令されなければ、ですが…。
その同一人物の中にある能力の不一致感が、一面的にしか人を見て判断しない社会においての、その人全体の信用を失わせる要因なのかなって気もします。
今から出すのは極端な例ですが、実際に自分も経験していて…
3桁の計算もできない、2秒前のことを逐一忘れる、そのループで買い物の会計もできない。
そんな人をたまに現実で見かけることは、多分誰にでもあると思います。
多分周囲もイライラすると思います。本人はおそらく脳に欠陥(失礼?)があり、手間取っている状態といえます。
その時の本人が感じているのは「恐怖、混乱、自罰、焦燥」基本的に健常者はそういった人間を急かしてしまうので、より時間経過で本人の「社会と自分への絶望感」を強固にします。
おせっかいに思うかもしれないけど、レジ前でそんな人を見かけたら会計を手伝ってあげてほしいです。その方がボランティアにもなるし効率が良いです。
とはいっても、そういうのに関わりたくない気持ちもわからなくもないが(急に牙を剥かれそうで)
③パートナーの存在を示唆され、途中で読むのを止めかけた
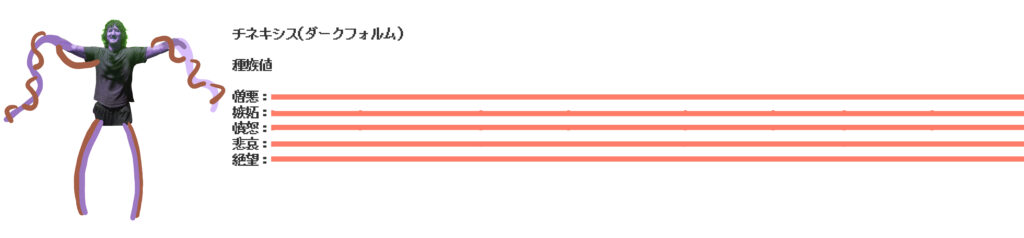
これはだいたい、障害や病気の人の体験レポとかにありがちなんですが、
救いの存在に
やっぱり…というかうんざりするが
相方(性的パートナー)の存在が出てきます(生えてきます)。
そこまで強調はされてませんが、鈴木さんは元健常者なので妻がいて、彼女と離婚せずに支えあったって話ですね。
この辺に関しては…、現実問題 性的パートナーがいる場合といない場合で人生の幸福度に10倍近い差がでる研究があった気がします。健常者でも同じ。
ぶっちゃけ 私が当事者の男だから言いますが、
男性の障碍者は ギフテッド以外 パートナーを得るのは 不可能です。 (一部特例はあるだろうが、いる人は神に感謝した方が善い)
社会学 心理学 生物学 科学がすでに証明している通りで この世の理として不変です。
弱い男は淘汰の対象、知識でなくても体感でわかる当事者も多いと思います。
こんな話は嫌い。
④生活保護について
本書にも取り上げられていました。これに関しては自分も当事者なので…
生活保護は、精神障碍者で誰も味方がいないなら容赦なく受けた方がよいです。というか強制でもよいくらい。
というのが私見だし、本書でも同じです。
よくネットやメディアの攻撃対象としてあげられる「生活保護」ですが、情報発信する側にも多面的な問題があり、それらの発信側はネガティブな一面を強化しているだけに過ぎません。
特にメディアは、生活保護者が特上の牛肉を食べてるのを映して、「働いてないのに贅沢している」という情報のみを報道してました。
まぁ今更ですが、テレビの情報を鵜呑みにしてる層って結構…障害とは言わなくとも境界知能か、なんかヤバいと思うので、特に言及はしません。
冷静に考えて、自分が滅びかけた時のセーフティーネットをディスる人間って多分「辛い思いをこれまでの人生で一切しなかった人」かなって思うんですが、それってゲームで例えるなら、「負けたり不利になったらリセットして問題が起こる前からリスタート」するのと同じくらい、現実だとありえないですよね。
それかどっかの研究室で楽園実験を受けてる被検体とか?
現実は「どんなク〇な状況でも生きなきゃいけない」のが正解です。だから生活保護があります。自分は無縁だと思わない方が多分賢いと思います。
ってなことを書いてたYO(嘘)。
⑤総評
良い本だと思います。
まぁでも…
想定する読者層がわかりづらいかなって思いました。
そもそも金持ってて本読むような知識階級は、こういう情報は取り入れないか、興味ないんじゃないかな。
でも 貧困層、そしてそれらの末路の 社会のダークサイド ヤクザや売春婦などのアウトローが、「実に度し難く、自分で自分を救う知恵も与えられなかった。いかに見放された人間たちであるか」がわかります。
正直、創作者である自分にとっては非常に有益で、世に言う悪の存在の裏設定にどれだけの悲劇があるか それを鮮明に描く材料に成りえると感じます。
自分が浅学菲才で、こんな感想文ではとても言うに表せぬ「当事者たちの持つ絶望感」が、本書にはあります。
そしてそれは今後も「解決不可能」だと思います、断言に近い 私見ですが。
本書にも記されている通り、弱者と救う側(福祉)には斥力があります。
それは「救われた経験が無い」「愛された経験がない」「満足した経験がない」という弱者のこれまでの人生で積み重ねてきた「社会からの敵意」みたいなものを、容易に捨て去ることができないからですね。
それは私も一部そう感じる部分があるので、共感します。
自分は子供の頃、同級生に将来 殺人鬼になるんじゃないかって言われるくらい捻くれた性格でした。
でも…
自分は大人になってから、「善い人を演じる」重要性を理解しました。それは学に恵まれている証拠です。高卒ですが…それでも恵まれている。
自分は「生活保護を受けている」けど、それは人に恵まれている証拠になります。障碍者ですが…まだマシ。
自分は「お金は少ないけど、足りている」それは やはり知恵があるからです。生活保護に陥って自罰から学び、向上心があったから、これも天恵。
本書を読んで一番思ったことは
まともな親、義務教育(なるべく高卒)、多少の知恵、そこから育まれる善良さ。それらを持ち合わせている自分は…社会の最底辺にいても尚、とても恵まれている存在だったことに気づかされました。
そして、
貧困含め 悪の側は救えないことにも気づいた。
何故なら
それはもう、その人の信念だから。多くの人が 親から愛されたうえで得た人格形成が正義の信念でも、その逆も然りです。
住む世界が全く違う。
私自身が 障害特性も相まってリバタリアン(自由主義)な理由も、自分が社会悪だとわかっているから、なるべく他人に迷惑をかけない”善い生き方”を心掛けるつもりで、個人能力重視の方針でいる。
そして当書はそんな私に、
できることとできないことを見極める
その重要性も、改めて学ばせてくれました。いわゆるニーバの祈りですね。
自分を社会に合わせても無駄なのは嫌という程 理解しているので、本当に頑張って生きたい いろんな意味で。
考えさせられる一冊でした。本当に、こんな記事の駄文からは想像もつかないほど良書だと思うんで、当事者も含め、そういう関係者にも読んでほしい!
以上です。
終。